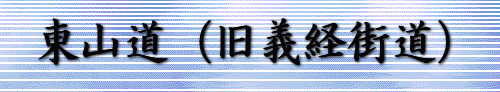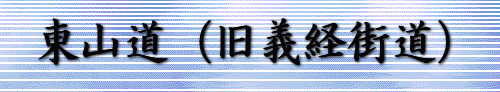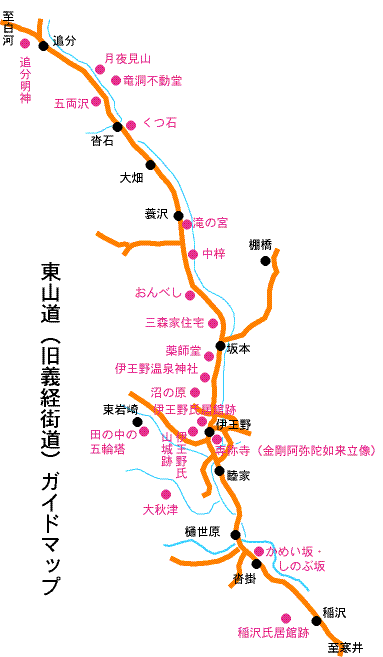| 東山道の繁栄と義経伝説古代から中世にかけて都と奥州の文化交流の幹となった旧東山道。義経街道ともいわれるこの道は、源義経が治承4年(1180年)兄頼朝の平家追討の挙兵に呼応して、奥州平泉を後に一路鎌倉へ向かった道である。この地には義経伝説をうらづける数多くのものが残されている。 |
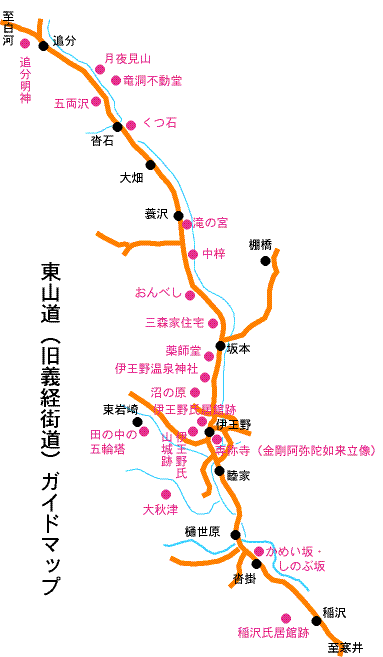 |
追分明神 |
| 古い国境にある峠神として信仰された。平家追討の祈願をしたと伝えられる。 |
| 月夜見山 |
| この山にかかった月を仰ぎ行く先の幸を祈ったという。 |
| 竜洞不動堂 |
| シドキ林道の奥300mの所にまつられており、別名白滝不動ともよばれている。 |
| くつ石 |
| 義経の愛馬のあしあとのある大石で、石の上には馬蹄形のくぼみがある。 |
| 滝の宮 |
| 蓑沢温泉神社で、創立は古く、滝があるので滝の宮と呼ばれている。ここで戦勝祈願をしたといわれる。 |
| おんべし(幣石神社) |
| 一行が休息し、武運を祈って御幣を岩上に安置したのでこの名が起こったという。 |
| 三森家住宅(国指定) |
| 長屋門と母屋が国の重要文化財の指定を受けている。関街道に沿った旧家で交代名主兼往来問屋としての住宅である。 |
| 薬師堂 |
| 堂内には町指定文化財の薬師如来立像と12神将が安置されている。 |
| 伊王野温泉神社 |
馬頭観音堂 |
伊王野城跡 |
| 霞ヶ岡にあり、拝殿前の神木杉2本は数百年の老杉でめずらしく、参道の杉並木は町文化財に指定されている。 |
義経の愛馬が病気になった時、供の常陸防海尊にこの堂の前で六日七夜馬の病気がなおるように祈願させたところ治ったといわれる。 |
伊王野家の中期から末期までの居城で霞ヶ城と呼ばれる。
|
| 専称寺 |
稲沢氏居館跡 |
|
| 伊王野家前葉の菩提所でその初期の墓がある。本尊の金銅善光寺式阿弥陀如来立像は国の重要文化財に指定されている。 |
那須氏の支家で伊王野氏祖次郎資長の弟五郎資家を祖とする稲沢氏の拠点であった。
|
|